動画内でご紹介した、FREEHANDさんの推しレンズのご紹介です!
FREEHANDさんの推しレンズは、
OMSYETEM M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO

です。
FREEHANDさんがなぜこのレンズを推しているのか?
何故このレンズを気に入っているのか、
何故このレンズにたどり着いたのか?
是非参考にしてみてください!
はじめに。
私の「推しレンズ」はOM SYSTEMのM.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PROです。
このレンズは、写真を撮り続けてきた中で、自然と「やっぱりこれだな」と思える存在になりました。
このレンズを推す理由を語るには、
私とレンズとの関係、そして試行錯誤の経緯に触れる必要があります。
かなり遠回りになりますが、まずはフィルム時代の話から始めさせてください。
フィルム時代
写真撮影は今よりはるかに若い頃からやっており、初めに使ったレンズはCanonのEF35-105mm F3.5-4.5というズームレンズでした。
他にも何本か使いましたが、単焦点レンズのEF24mm F2.8を最もよく使っていました。
デジタルカメラ
その後一旦写真撮影を離れ、
20年くらいのブランクがあり、各社がミラーレスシフトをしている真っ只中の2018年、
初めてレンズ交換式のデジタルカメラを購入することにしました。
その時、最初の一本として選んだのはM.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8でした。
なぜ45mm(35mm判換算で90mm)なのかといえば、初めに使った105mmの画角に近いということ、24mmを使った経験から広角は広すぎると感じたことなどからです。
中望遠の画角は、対象を適度に切り取ることができ、
広角と違って余計なものをフレームの外へ追いやることがやりやすい。
被写体をちょっと注視する感じ、それがいいと思ったのです。
ズームレンズではなく単焦点を選んだ理由もフィルム時代の経験にあります。
当時のズームレンズに対する「描写が甘い」という印象が残っており、
安価でも単焦点レンズの方がマシではないか?と考えたのです。
また、なぜ初めからPROレンズを選ばなかったのかといえば、
それはデジタル時代の機材に対する知見が全くなかったからです。
レンズの選択にあたって、ネットで作例をいくつも見ましたが、フィルム時代の写真と比べると、どれもはるかにキレイだと思ったので、わざわざ高価な機材を購入する必要性を感じませんでした。
45mm F1.8についての気付き
このレンズは、軽くて、描写も悪くなく、コストパフォーマンスも高いレンズでした。
しかし、使い続けるうちに幾つかの不満点も見えてきました。
まず防塵防滴ではないこと。ボディが防塵防滴でもレンズが非対応だと意味がありません。
実際、小雨を浴びるとカメラが動かなくなります。
温室で撮影することがよくありますが、温室内に小さな滝の設備があり、
そこに近づくとやはり動かなくなります。
また、画面全体がフレアっぽくなります。
霞がかかったように白っぽくなるのです。
多くの作例を見てきたことで、そのような違いも分かるようになってきました。
フレアの原因はおそらく、
レンズのコーティングやレンズ内部の反射を防止する措置の違いなのだろうと思いました。
この時、価格の違いによる機材の作りの違いを意識しました。
フレアっぽい画像はレタッチで改善できるのですが、
撮影プロセス全体を通して考えるとストレスになります。
PROレンズ
そんな中、あるYouTube動画との出会いがありました。
海外のプロと思われる写真家が45mm F1.8とF1.2 PROの比較をしているものでした。
言葉はわかりませんでしたが、作例を見た瞬間にそれらの違いがわかりました。
F1.2 PROの方はフレアっぽい感じが全くなく、コントラストがよく、何より独特の雰囲気があると感じました。
それ以降、ネットでこのレンズの作例をいくつも調べると、やはり同じような印象を受けました。
単にシャープというだけでなく、
光がレンズのガラスの中をきちんと通ってきたような感じがしました。
そのガラスによって独特の味付けがなされているようにも感じました。
}そのようなことから購入を決意しました。
使ってわかった違い
最初にこのレンズを使ったボディはOLYMPUSのOM-D E-M5 Mark IIでした。撮ってみてすぐに、これまで感じていた不満は解消されたと思いました。
それだけでなく、
この描写であればフルサイズに乗り換える必要もないのではないか、とすら思いました。
ただ一つの不満点は、もう少し寄れたらという点です。花を撮ることが多かったので、
こう思うことはよくありました。
接写リング、ズームレンズ、マクロレンズとの比較
その「もう少し寄りたい」という欲求から、接写リングを試しました。
しかし、ピントの合う範囲が狭くなるという制約があり、これは断念しました。
そこで一旦45mm F1.2PROを手放し、
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO(初期型)を購入しました。
これは45mm F1.2PROよりも寄れます。
ズームは現代では描写も改善されているだろうと期待したのですが、
使ってみるとやはり違和感が残りました。
具体的には「まるで光が一度回り道をしてから、ようやく像を結んでいるような感覚」でした。解像度が悪いとか収差があるということではなく、感覚の問題です。
単焦点レンズでは安価なものであってもこのように感じたことはありませんでした。
ボケについては、悪いということはないのですが、
接写した時、
ピント位置から少しはずれたところに粒のようなボケが現れることがあり、
それが気になりました。これは今まで使ってきたどのレンズでも見たことがありませんでした。
また、ズームレンズを使った撮影では、画角の感覚が曖昧になることがありました。
光の状態の良い被写体を見つけて、位置をとり、カメラを構えてアングルや構図を決める。
その時、光と被写体と画角の関係が一つにまとまる、
このような一連の流れがうまくいかないと感じました。
その後ズームではなく、60mmのマクロレンズも試しました。
これは逆に寄れ過ぎて、これまでやってきた「被写体があって、背景がある」という絵作りとは全く異なる世界だと思いました。
接写すると被写体と背景の区別がなくなるのです。
この世界に踏み込もうという気は起きませんでした。
被写体から離れて使う場合も、
35mm判換算で120mmという焦点距離は私にとっては長すぎると感じました。
開放F値
単焦点の45mmの開放F値はF1.8、F1.2でした。
これに対してズームレンズ、マクロレンズはともに開放F値が2.8と、やや暗いものでした。
この違いも実際に使ってみて戸惑った点でした。
私の撮影は基本的に、マニュアルモードでISO感度は200、絞りは開放で、
明るさをシャッタースピードで調整しています。
屋外の撮影で日が陰ってきたときや、温室内で撮影している時、
ズーム、マクロの場合はシャッタースピードをかなり遅くする必要があることに気付きました。
レンズの開放F値が暗いからです。
シャッタースピードを遅くした場合の問題ですが、手ブレに関してはボディ内手ブレ補正があるので、その心配はほぼありません。
しかし、風に揺れる花の動きを確実に止めるためには、
それなりのシャッタースピードを確保しておきたいところです。
そのためにISO感度を上げてシャッタースピードを早くする方法もありますが、ISO感度を上げるとダイナミックレンジが狭くなったり、ノイズが増えたりしますので、なるべくカメラの標準感度である200にしておきたいです。
温室では花が風に揺れることはほぼありません。
しかし、ガラス張りの屋根から光が入ってくるとはいえ、積んである岩の陰になったり、
トンネル状の暗い部分があったりと、さすがに屋外とは明るさが違います。
思った以上に写真が暗くなることが多く、
そこで改めて「開放F値」の差が大きく影響していると実感しました。
再びPROレンズ
このような経緯を経て、やはりこれだと思って45mm F1.2 PROを再度購入することにしました。
もちろん、寄れないことに変わりはありませんが、その制約も含めて受け入れることにしました。
同じタイミングで、より使いやすい機材を揃えたいと思い、ボディもOM-1に変更しました。
また、M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PROも購入し、
現在では広角と中望遠の2本体制で撮影をしています。
これはKen Rockwell氏の「シンプルということ」という記事を読んだ影響もあります。
日本語訳されたもののURLを記載しておきますので、興味があればぜひご覧ください。
https://blue-period.hatenadiary.org/entry/20131013/1381670801
少数精鋭のレンズで対象に向き合う、そのようなスタイルが自分には合っていると思います。
おわりに
「推しレンズ」として45mm F1.2 PROを挙げる理由は、
単に描写の良さやスペックの良さだけではありません。
写真撮影を続けてきた過程において、
手放してもまた戻ってきたことが示すように、
まさに「切っても切り離せない存在」だと言えます。
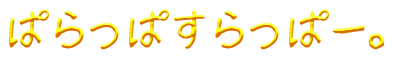
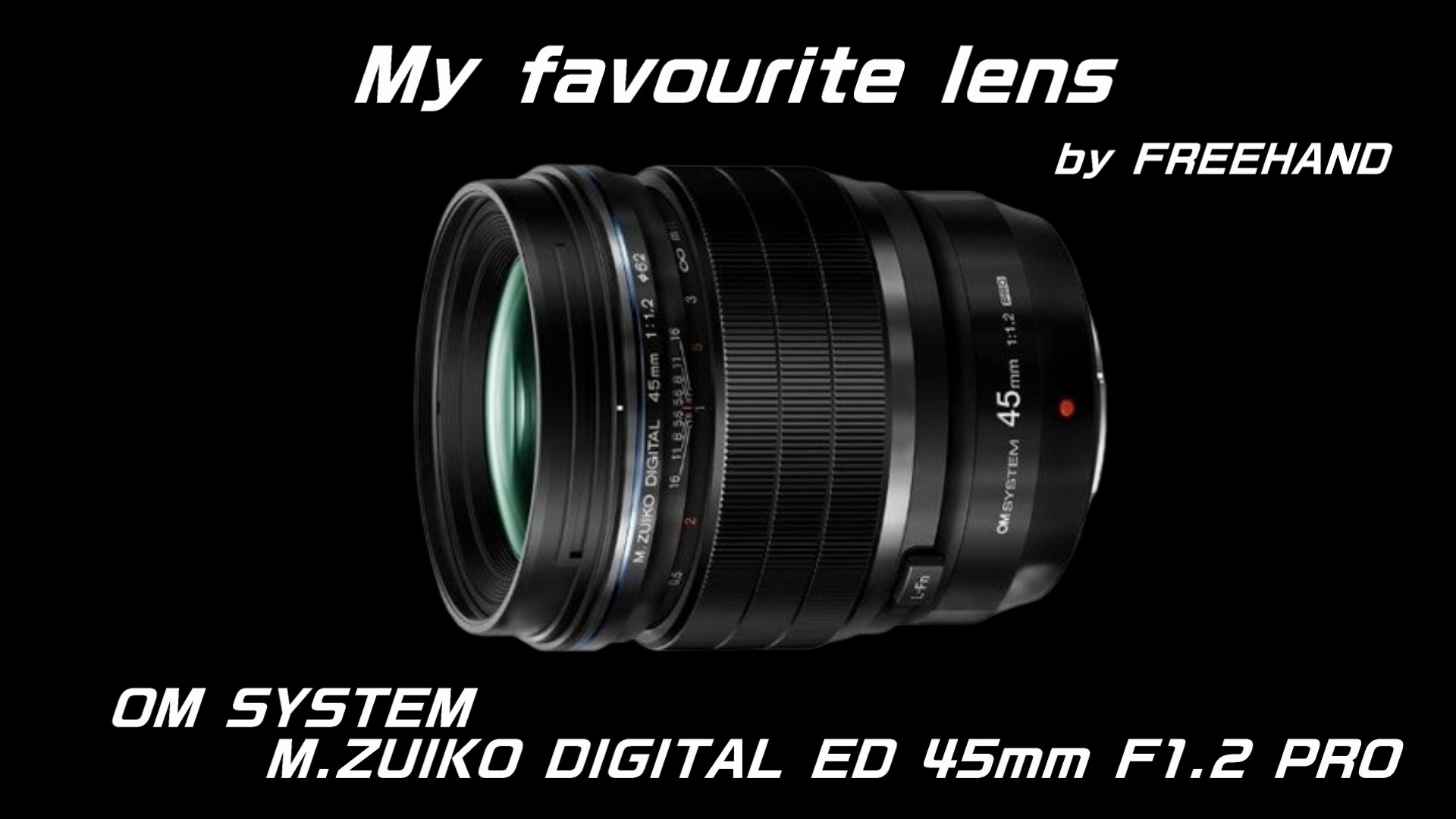


コメント